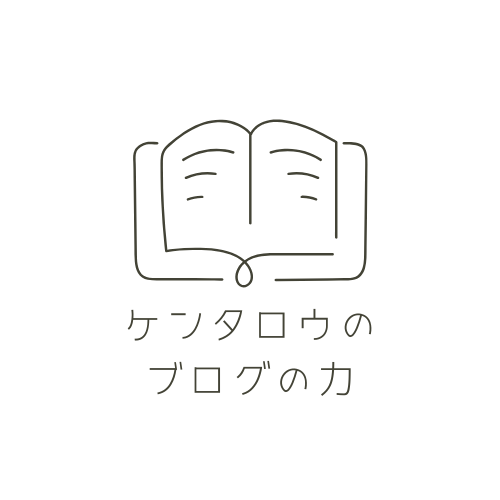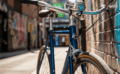友田オレさんの「どうにかできたはず」という楽曲について、その原曲が何なのか、気になって検索された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この歌は、耳に残るメロディと共感を呼ぶ歌詞で、彼の代表的なネタとして広く知られています。
この記事では、「友田オレ どうにかできたはず 原曲」という疑問に答えながら、楽曲が生まれた背景や、彼の魅力的な芸風についても詳しく解説していきます。
初めて友田オレさんを知った方にも分かりやすく、このユニークな楽曲の世界観をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
友田オレさんの「どうにかできたはず」原曲を解説!
「どうにかできたはず」はオリジナル曲?
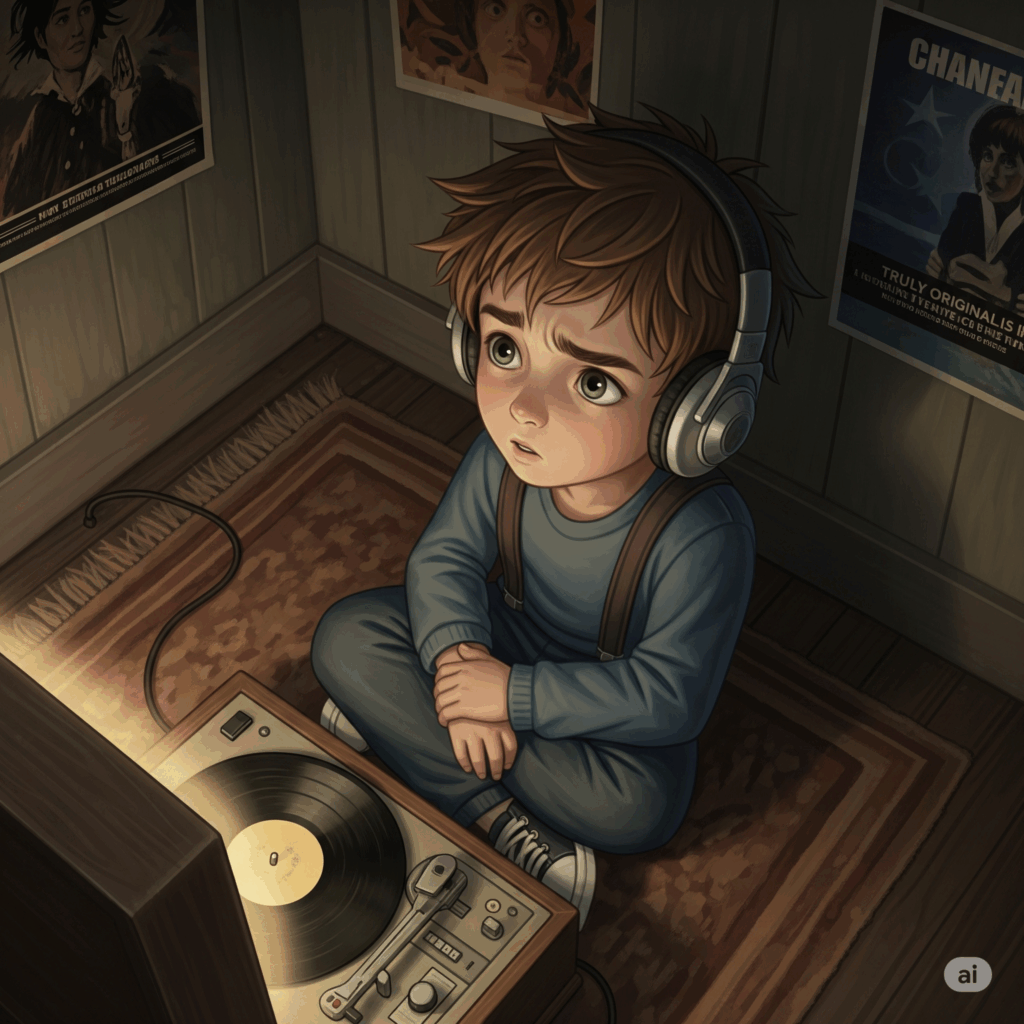
友田オレさんの代表曲である「どうにかできたはず」は、彼のオリジナル曲です。この曲は、市販の楽曲の替え歌ではありません。
友田オレさん自身が、幼馴染である音楽活動をしている友人に依頼して作曲してもらったオリジナルのメロディーが使われています。
これは、プロの芸人として活動する上で著作権などの権利関係をクリアにするためです。
アマチュア時代には替え歌ネタを披露することもあったようですが、プロ転向後はオリジナルの楽曲を使用することで、より自由に表現活動を行うことができるようになったと言えるでしょう。
この楽曲は、友田オレさんのネタの重要な要素であり、彼の独特の世界観を形成しています。
歌詞に込められた意味とは?
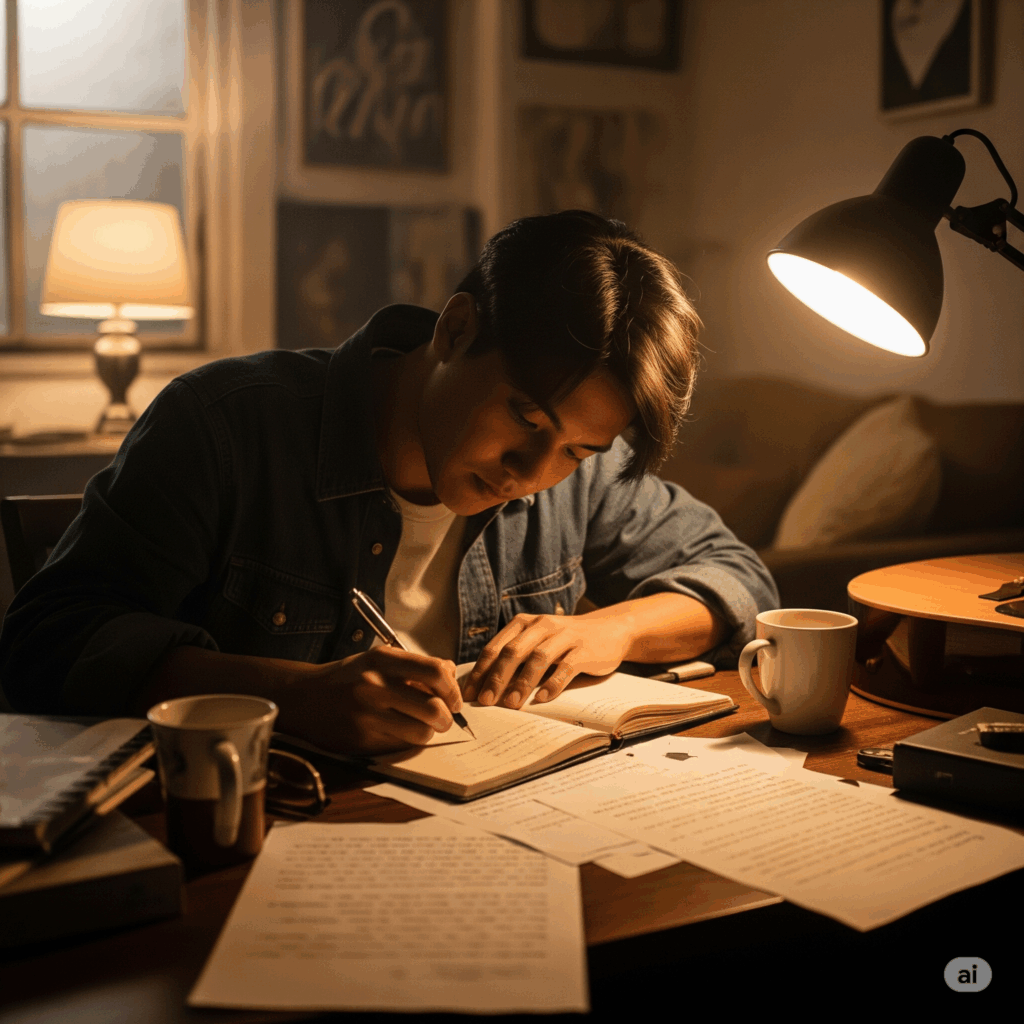
「どうにかできたはず」の歌詞には、日常の中で「なぜこうなってしまったのだろう」「もう少し何とかなったのではないか」と感じるような、些細な出来事や歴史上の事実に対する後悔や疑問が込められています。
例えば、駅のホームで引き止められなかったことへの未練や、元横綱・双羽黒の引退劇、さらにはスポーツチームの愛称のすり合わせ不足など、多岐にわたるテーマが取り上げられています。
これらの出来事に対して、歌詞は一貫して「どうにかできたはず」「すり合わせできたはず」「アプデとかできたはず」「どこか削れたはず」「どうとでもできたはず」というフレーズを繰り返します。
この繰り返しが、聞く人に共感や、時にはツッコミを誘うようなユーモラスな効果を生み出しているのです。友田オレさんは、この曲を通じて、リスナーが「聞いていて心地いい」と感じることを大切にしていると言います。
また、聞けば聞くほど、噛めば噛むほど味が出るような、スルメのような楽曲を目指しているとも語っています。
決勝ネタで披露された背景
友田オレさんが「どうにかできたはず」を初めて全国区の舞台で披露したのは、2023年のABCお笑いグランプリ決勝でした。この大会は若手芸人にとって大きな登竜門であり、友田オレさんは当時現役の大学生でありながら決勝進出という快挙を成し遂げました。
このとき披露されたネタが「どうにかできたはず」であり、その独特の歌ネタとフリップを組み合わせたスタイルは、多くの視聴者に強い印象を与えました。
彼のネタは、既存のヒット曲の替え歌ではなく、オリジナルの楽曲にのせて世の中の「どうにかできたはず」な出来事を羅列していくというものです。
この手法は、耳に残るメロディーと共感を呼ぶ歌詞が相まって、一度聞くと忘れられないインパクトを残しました。
特に、テレビの全国放送でこのネタが披露されたことで、友田オレさんの知名度は一気に上昇し、彼の芸風を確立するきっかけの一つとなりました。
友田オレの大学時代と楽曲制作
友田オレさんは、早稲田大学文化構想学部を卒業しています。彼がお笑いの道を志したのは、大学にお笑いサークル「お笑い工房LUDO」があることを知り、そこで活動することが目的の一つでした。
大学1年生でLUDOに所属し、最初はコンビを組んでいましたが、2年生の時に相方が卒業したことをきっかけにピン芸人としての活動を始めました。
「どうにかできたはず」のような歌ネタの制作は、プロ転向後に本格化しました。
アマチュア時代には替え歌を披露することもあったものの、プロとして活動するにあたり、著作権の問題を避けるためオリジナル楽曲が必要となりました。
そこで、音楽活動をしている幼馴染に作曲を依頼するようになったのです。友田オレさん自身がイメージする「こんな感じにしたい」という要望を伝え、幼馴染がそれに合わせて作曲するという形で、現在の楽曲が制作されています。彼は音楽理論には詳しくないと言いますが、「聞いていて心地いい」ことを重視して楽曲制作に取り組んでいるそうです。
友田オレ「どうにかできたはず」原曲と彼の魅力
友田オレのユニークな芸風
友田オレさんの芸風は、歌とフリップネタを組み合わせた非常にユニークなスタイルが特徴です。彼が披露するネタは、耳に残るメロディーに乗せて、日常の中のちょっとした疑問や、歴史的な出来事に対して「どうにかできたはず」といったツッコミを入れるものです。
フリップに描かれたイラストと歌詞の内容が絶妙にマッチしており、視覚と聴覚の両方から楽しませてくれます。
彼の歌声はキーが高く、とても聞き心地が良いと評判です。
友田オレさん自身も、ネタ作りにおいて「聞いていて心地いい」という点を重視していると語っています。また、一度聞いただけで終わらず、何度も聞きたくなるような、いわゆる「スルメ」のような面白さを追求しているそうです。
このような独自のスタイルは、他の芸人とは一線を画しており、彼の大きな魅力となっています。
本名は?芸名の由来について
友田オレさんの本名は、**松延(まつえのぶ)**さんです。彼の芸名である「友田オレ」は、非常に個性的で一度聞いたら忘れられない名前ですが、その由来は意外にもシンプルなものです。
早稲田大学時代に受けていた講義を担当していた教員の名字から「友田」をとり、そこに「オレ」という言葉を組み合わせて「友田オレ」と名付けられました。
特に深い意味や売れるためのジンクスを意識したわけではなく、何となく組み合わせた結果だそうです。しかし、「友田オレ」という響きが、時に「共倒れ」と聞こえるという点も、かえって記憶に残る要因となっているのかもしれません。
彼の独特な芸風と相まって、このインパクトのある芸名もまた、友田オレさんのキャラクターを形作る重要な要素となっています。
「面白くない」と言われることも?
友田オレさんのネタは、その独創性から「面白い」と高く評価される一方で、一部では「面白くない」という意見を聞くこともあるかもしれません。
彼の芸風は、歌とフリップを組み合わせたリズムネタであり、特定の出来事に対する皮肉や共感を誘う内容が特徴です。このようなスタイルは、すべての人に instantly 響くとは限らない場合があります。
一般的な漫才やコントとは異なるアプローチであるため、初めて彼のネタに触れる人の中には、その意図や面白さを理解するのに時間がかかる方もいるでしょう。
しかし、これは彼の芸風が独特であることの裏返しとも言えます。繰り返しネタを観ることで、その奥深さや、彼が目指す「噛めば噛むほど味が出る」面白さに気づくことができるかもしれません。
友田オレさん自身も、自身のネタについて「犬にとっては骨」のような存在だと表現しており、じっくりと味わうことで真価が発揮されるタイプだと言えるでしょう。
友田オレの今後の活動
友田オレさんの今後の活動は、R-1グランプリ2025での優勝を機に、さらに多岐にわたるものと予想されます。彼は史上最年少、かつ史上最短芸歴でR-1グランプリを制覇したことから、お笑い界の新しい顔として注目を集めています。
現在も、テレビやラジオ、配信コンテンツなど、様々なメディアに出演しており、その露出は今後さらに増えていくことでしょう。
彼はピン芸人としての活動に加え、ピボット福田さんと「Let Me Show You THE まごころ」というコンビを組み、漫才も披露しています。
このことからも、彼の芸に対する探求心や表現の幅広さがうかがえます。また、音楽活動も継続しており、幼馴染とのコラボレーションによる楽曲制作も続くものと考えられます。
彼の独特な感性と表現力は、今後も多くの人々を魅了し続けるでしょう。