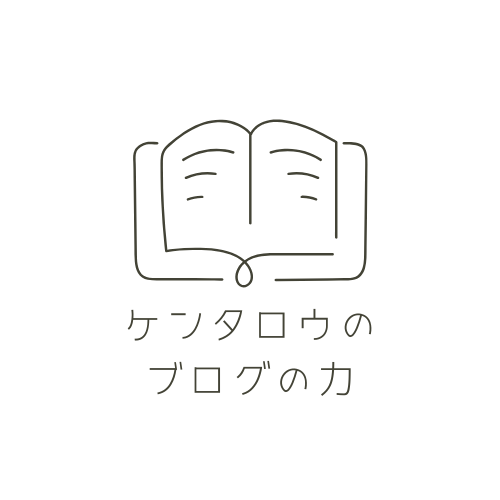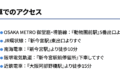広島女学院大(広島市東区)が27年度に共学化することを発表しました。
理由は2026年4月より学校法人YIC学院へ経営を移行し、YICが共学化する方針としたためです。
大学施設はそのまま継続するので
- 26年度 入学生 → 広島女学院生として卒業
- 27年度 入学生 → 新共学校として卒業
となります。
ちなみに27〜29年度までは、女学院と共学が同じ大学内に併存する形になります。
ではなぜ、
下記に解説していきたいと思います。
女子大が減少している理由は?大きく5つ
- 少子化による18歳人口の減少: 大学進学希望者自体が減少しているため、特に女子学生を対象とする女子大学は学生確保が厳しくなっています。
- 共学志向の高まり: 多くの高校が共学化しており、女子学生も共学の大学に進学することに抵抗が少なくなっています。また、多様な学びや交流を求める学生が増えていることも背景にあります。
- 実学・理系志向の高まり: 従来の女子大学に多かった人文科学や家政学系だけでなく、社会でより実践的なスキルを身につけられる実学系(経営、経済など)や、理系分野(看護、医療、情報系など)の人気が高まっています。女子大学ではこうした学部の設置が遅れたり、もともと少なかったりする傾向がありました。
- 「総合大学」志向の高まり: 多くの学部や学科を持つ総合大学の方が、幅広い学びの選択肢があることや、より大規模な環境で多様な学生と交流できるという点で人気を集めています。
- 男女雇用機会均等法の成立と社会の変化: 男女の雇用機会が平等になり、女性が社会で活躍する場が広がったことで、女子大学で学ぶことの意義が相対的に薄れたと感じる学生が増えたことも影響しています。就職先の選択肢も増え、あえて女子大学を選ぶ必要性を感じにくくなっています。
- 統廃合や共学化への移行: 経営の厳しさから、他の大学との統合や、男女共学化に踏み切る女子大学が増えています。
これらの要因が複合的に絡み合い、女子大学の減少につながっています。
共学化した大学は?
代表的な例としては、以下のような大学が挙げられます。
- 武蔵野大学(旧:武蔵野女子大学): かつては文学部を中心とした仏教系の女子大学でしたが、共学化を経て多くの学部を増設し、今では大規模な総合大学として知られています。
- 京都橘大学(旧:京都橘女子大学): 武蔵野大学と同様に、共学化後に経済・経営・工・看護・教育など多岐にわたる学部を設置し、京都を代表する総合大学の一つとなっています。
- 文京学院大学(旧:文京女子大学): 経営学部が初めて女子大学に設置されたことでも知られましたが、男女共学化し、看護・医療系の学部も増設して総合大学となりました。
- 京都光華大学(旧:京都光華女子大学): 2026年度から男女共学化し、名称も変更する予定です。
- 岡崎大学(旧:岡崎女子大学): 2026年度より共学化し、名称も変更する予定です。
- 園田学園大学(旧:園田学園女子大学): 2025年度から段階的に共学化を進め、2028年度には完全共学化を目指しています。
これらの大学は、共学化によって学生の多様性を促進し、新たな分野の学部を設置することで、時代のニーズに応え、志願者数の増加にも成功している事例が多く見られます。
女子大学が共学化に踏み切る背景には、学生確保の厳しさだけでなく、より幅広い学びの機会を提供し、社会の変化に対応していくという大学側の意図も強くあります。
人口が減少しているのに大学がなぜ増えている現象
ではなぜ、人口が減少傾向にあるにもかかわらず大学が増加しているのでしょうか?
主な理由を以下に挙げます。
- 大学進学率の上昇と「大学全入時代」:
- 少子化が進む一方で、社会の変化に伴い、より高度な教育が求められるようになり、大学進学への意欲が高まっています。結果として、18歳人口が減少しても、大学進学率自体は上昇傾向にあります。
- これにより、多くの大学が定員割れを起こす一方で、「大学全入時代」と呼ばれるほど、希望すれば誰でも大学に入れるような状況になりつつあります。これは、大学が学生確保のために、より多様な学生層を受け入れようとしている側面も示しています。
- 社会構造・産業構造の変化と人材ニーズの多様化:
- かつては終身雇用が前提で企業が社内で人材育成を行うのが一般的でしたが、現代では企業は即戦力を求める傾向が強くなっています。
- 情報化社会の進展や技術革新により、特定の専門知識や実践的なスキルを持つ人材の需要が高まっています。これに対応するため、大学は学部・学科の多様化や、より専門性の高い教育プログラムを提供しようとしています。
- 特に、近年では「専門職大学」のように、特定の産業分野における実践的な職業教育に特化した大学も新設されており、これも大学数の増加に寄与しています。
- 大学設置基準の緩和:
- 文部科学省による大学設置基準の緩和も、大学数の増加の一因とされています。これにより、大学の設置が比較的容易になり、既存の大学も学部・学科の再編や新設がしやすくなりました。
- 過去には定員管理の厳格化が進められましたが、近年ではその緩和の動きも見られ、大学の設置や拡充に柔軟性を持たせています。
- 地方創生への貢献:
- 地域における「知の拠点」として、大学が地方創生に果たす役割への期待が高まっています。地方自治体や産業界との連携を通じて、地域に必要な人材の育成や産業の振興、地域課題の解決に貢献することが求められています。
- 地方の大学が、地域の活性化を目的として新設されたり、既存の大学が地域に特化した学部を設置したりするケースも見られます。
- 生涯学習・リカレント教育のニーズ:
- 社会人の学び直し(リカレント教育)や生涯学習へのニーズが高まっています。これに対応するため、大学が社会人向けのプログラムやコースを新設したり、オンライン教育を拡充したりする動きも、大学の多様化や増加につながっています。
これらの要因が複合的に作用し、少子化が進む中でも大学数が増加するという状況が生まれています。しかし、その一方で、定員割れの大学が増加し、大学間の格差が拡大するという課題も顕在化しています。
女子大と共学が併存することは可能?
女子大学が共学化する際に、女子大学と共学の学部が併存する形は可能ですし、実際にそのような移行を進める大学も存在します。
完全に全学部を一斉に共学化するのではなく、段階的に移行するケースが多いです。その方法としては、以下のようなパターンが考えられます。
- 一部の学部のみを共学化する:
- 特定の学部(例えば、社会のニーズが高い看護学部や情報学部など)を共学化し、他の学部は女子大学として維持する。
- これにより、大学全体のイメージは共学に近づきつつも、従来の女子教育の伝統を残すことができます。
- 例としては、清泉女学院大学が看護学部のみを共学化しています。
- 新設学部を共学とする:
- 既存の学部は女子大学のまま残し、新たに設置する学部から男子学生を受け入れる形。
- これは、新しい学びの分野を開拓しつつ、従来の女子学生の環境を大きく変えないための方法として有効です。
- キャンパスを分けて共学化を進める:
- 完全に異なるキャンパスに共学の学部を設置し、従来のキャンパスは女子大学のまま運用するなど、物理的に分離することで併存させるケース。
- ただし、これはキャンパスの確保や運営コストの面でハードルが高い場合があります。
- 段階的に全学部を共学化する:
- 数年かけて、順次すべての学部を共学化していく計画を立てる。この期間中は、まだ共学化されていない学部は女子大学のまま、共学化した学部と併存することになります。
- 園田学園大学が2025年度から段階的な共学化を進める予定であることがその例です。
女子大学と共学が併存することのメリットとデメリット
- メリット:
- 伝統と新規性の両立: 女子教育の伝統や培ってきた強みを維持しつつ、共学化による多様性や新たな学生層の獲得を目指せます。
- 学生の選択肢の広がり: 女子大学を志望する学生と共学を志望する学生の双方に門戸を開くことができます。
- 急激な変化の緩和: 大学の文化や教職員の意識を徐々に共学環境に適応させていくことが可能です。
- デメリット:
- アイデンティティの曖昧さ: 「女子大学なのか共学なのか」という大学のアイデンティティが不明確になる可能性があります。
- 学生間の摩擦: 女子学生と共学化された学部の男子学生の間で、文化や学習環境に関する摩擦が生じる可能性もゼロではありません。
- 広報の難しさ: 併存している状態を学生や保護者に分かりやすく伝えるのが難しい場合があります。
多くの女子大学が共学化に踏み切る背景には、単に学生数を確保するだけでなく、社会の変化に対応し、より多様な学びの機会を提供しようという意図があります。そのため、それぞれの大学が独自の戦略をもって、共学化の形態を選択しています。